吉田松陰2 「留魂録」の後
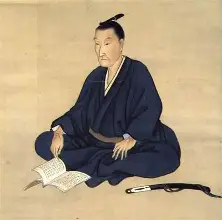
――――前回において、紹介しましたとうり、松陰先生は『留魂録』をお書きになって、翌日に処刑されて「武蔵野の野辺」に散りゆかれました。 ご紹介しました『留魂録』ですが、8番目の文章を紹介しました。しかし『留魂録』は、これのほか全部で16からの文面で構成されております。是非ともお読みくださいますようお願いいたします。 そして、『留魂録』は、この最後に文面を持って結ばれております。
「かきつけ終りて後
心なることの種々かき置きぬ
思い残せることなかりけり
呼びだしの声まつほかに今の世に
待つべきことのなかりけるかな
討たれたる吾れをあはれと見ん人は
君を崇めて夷払へよ
愚なる吾れをも友とめづ人は
わがとも友とめでよ人々 七たびも生きかへりつつ夷をば 攘はんこころ吾れ忘れめや」
十月二十六日黄昏書す 二十一回猛士
――――この『留魂録』を書き上げた翌日、処刑されていくわけです。しかし、この残された一日と言う、時間の中にも、凄いドラマが御座いました。その辺を松浦光修著「日本の心を思い出す六つ」の中から引用させて頂きます。
松陰先生は、短い生涯の中で、膨大な量の文章を書き残されております。 ご紹介した『留魂録』(8章、前回で記載)の一節は、その中でも最高級の名文です。 人間とは、‟自分の死”を、これほどまでに静かで、美しい心で迎えることの出来るものか・・・、と思わせられる一文です。明日にでも処刑される‟極限状態”でありながら、その一文には、どことなく不思議な明るさと、透明感さえ漂っています。「安心立命の境地」とは、こういう事をいうのかも知れません。松陰先生は、ここで、自分の人生を、一粒の種もみに例えています。私が死んでも、私の志を継ぐ者が現れれば、それは私が、立派な「種もみ(原文「後來の種子」)で有った。・・・と言う事にもなります。」と書かれております。
時代も場所も飛びますが、新約聖書の「福音書」の中で、イエス・キリストが、こんな言葉を語られております。 「一粒の麦は、地に落ちて死なねば、いつまでもただの一粒である。しかし、良い地に落ちて死ねば、多くの実を結ぶであろう。」(ルカの福音書) 「自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、私のため、また福音のために命を失う者は、それを救うのである」(マルコの福音書) 「私は、あなた方のために命を捨てる。友人のために命を捨てる以上の愛はないのだ。」(ヨハネによる福音書)
奥深い言葉です。抜きん出て高い精神性の境地に達した人の言葉には、やはり、どこか共通するところがありますまいか。つまり、松陰先生を始めとして、幕末維新から大東亜戦争にかけて散華した志士や英霊達は、実は”それ以上のものはない”と言う程の「愛」に満ちた人達で有ったのです。
問題は、今に生きている私達です。果たしてどうか・・・、と言う事です。 私達はその様な祖国の先人達の、高い志を受け継いで生きている「種モミ」と言えるでしょうか! また、私達は「中身の詰まった種モミ」の様な人生を送れているでしょうか?
二十歳代で「安心立命の境地」で、「武蔵野の野辺」に散りゆかれました、松陰先生の「死生観」の学びを、もっともっと深めたいものです。
【留めおかまし 大和魂】 さて、処刑の時は迫ってきます。松陰先生は同士にあてて、最後の著作を書き始めました。それが『留魂録』です。 十月二十五日から書き始め、書き終わったのが二十六日の夕方・・・つまり、ほぼ二日で書き上げた訳です。書き上げた翌日の二十七日、松陰先生は三十歳(満二十九歳)で「武蔵野の野辺」に散ります。 『留魂録』の中の「四時の説」は次のような有名の和歌から始まります。
「身はたとひ 武蔵野の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」 (歌意―――「たとえ私の身は、武蔵野の野辺で朽ち果てようと、私の魂は、永遠にこの世にとどまらせて、祖国、日本を護らせて下さい。」) そして、その後に、次のようなことが書かれています。 「結局のところは、私の力が足りず、何も成し遂げることが出来ないまま、今日のような事態に至りました。それもひとえに、私の人徳や才能が無かったせいです。今さら誰を咎めようという気もありません。また、誰を恨もうという気も有りません。」
松陰先生は、これも好きな言葉の一つであり、信じていました。 「至誠にして動かざるものは、未だ之あらざるなり」『孟子』(歌意―――「誠を極めれば、その力によって動かしえないようなものは、この世の中には一つもない」)しかし、結局は「死罪」となります。そのことについて、松陰先生は、この様に考えるのです。‟この『孟子』の言葉が間違っていたのではない。私の誠の心が、まだまだ足りず、それで、天地を動かすことが、出来なかっただけだ”と・・・ですから、ここに書かれているように、死に臨んでも、恐れ、怨み、呪い、怒り、憎しみ、などの負の感情は有りません。むしろ、心は清々しさに満ちています。
松陰先生は、『留魂録』の中で、同志に託したことを書き、最後を五首の和歌で締めくくります。その内の一首を、あげておきます。 「呼び出しの 声待つ外に 今の世に 待つべき事の なかりけるかな。」 (歌意―――「処刑を言い渡すための呼び出しの声が、もうすぐかかるでしょう。今の私は、その声を待つことのほか、もはや何もする事は有りません。」)
松陰先生が待っていた「処刑を言い渡すための呼び出しの声」がかかります。それを聞いて、また、筆を取り、ふところに入れていた紙に、こう書きつけました。 この一筆も、現物が残っているのですが、その写真版を見ますと、実に落ち着いた流麗な筆跡に、驚かされます。 その後、松陰先生は、あわただしく評定所に引き立てられ、死刑の判決を受けたあと、大きな声で『留魂録』のはじめに掲げられている「身はたとひ 武蔵野の野辺に 朽ちるとも 留め置かまし 大和魂」と共に、更に新たにつくられた漢詩を、朗々と吟じられたのです。 その漢詩を聞いた人が、それを書き留めて、今に伝えられています。その漢詩はタイトルは有りませんが、今では「辞世」と言われています。
『吾、今、国の為に死す、死して君親に背かず、悠々たり天地の事。鑑照は明神に在り』
(歌意)「私は、これから国の為に死にます。死んでも、主君や両親に対して恥ずべきことは何も有りません。もはや、私は、この世のあらゆることを、のびのびとした気持ちで受け入れています。今、私は私の人生の全てを、神々の照覧にゆだねます。」
この「辞世」は、わずか漢字二十字のものですが、そこには、松陰という人の人生全てが、美しく結晶化しているように思はれます。
松陰先生の最後の様子について、そこに立ち会った長州藩士・小幡高政の談話が残っています。 「奉行などの幕府の役人たちは、正面の上座に並んで座っていました。私は、下の段の右脇の場所に、横向きに座っていました。しばらくして松陰が、潜戸から護送の役人に導かれて入って来ました。そして、決められた席につき、軽く一礼すると、並んでいる人々を見渡しました。髪と髭は、ボウボウに伸びていました。しかし、眼光は炯炯として、前に見た時とは別人の様でした。その姿には、何というか・・・一種の凄味が有りました。 直ぐに死刑を申し渡す文章の読み聞かせがあり、その後役人が松陰に「たちませい!」と告げます。すると、松陰は立ち上がり、私の方を向いて、微笑みながら一礼して、再び潜戸から出て行ったのです。 すると、その直後、朗々と漢詩の吟ずる声が聞こえました。それは『吾、今、国の為に死す、死して君親に背かず。悠々たり天地の事。鑑照は明神に在り』との漢詩です。 その時、まだ幕府の役人達も、席に座ったまま、厳粛な顔つきで襟を正して聞いていました。私は、まるで胸をえぐられるような思いでした。その後、松陰は駕籠に入れられ、伝馬町の獄に向かいました」
そして、松陰先生は正午ごろ、一度、伝馬町の獄に戻り、いよいよ処刑場に向かいます。斬首去れる時の様子は、依田学海(百川)という漢学者の日記に、八丁堀の同心、・吉本平三郎から聞いた話として、この様に書かれています。
「先頃、死罪になった吉田寅次郎(松陰)の振る舞いは、皆感動して、泣いていました。奉行から死罪が言い渡されると「かしこまりました。」と丁寧に答えて、ふだん評定所に行くときに介添えしてくれていた役人にも「長らくお世話になりました。」と優しくいったそうです。 そして、いよいよ処刑という時、「鼻をかませてください」と言いました。そして、その後は心静かに構えて、首を討たれたそうです。 そもそも死刑になった者は、これまでたくさんいましたが、これほどまでに落ち着いて死んでいった者は、見たことがありません。」
こうして、松陰先生は、見事に人生の幕をとじました。そののち、高杉晋作は幕府という‟先生の仇”を討たずにおくものか・・・、と誓っています。他にも、松下村塾で学んだ数多くの、門人たちが‟先生の仇”を討つために立ち上がったのです。約43名の門人たち、多くは最後、非業の最期を遂げます。しかし、それらの、無数の屍の上に、しだいに明治という新しい時代の、夜明けの光が差し始めるのです。 そのように、歴史を見ると、松陰先生の『留魂録』は、どうやら、「武蔵野の野辺」に留まる事なく、門人たちに添い、門人たちの魂を燃え上がらせ、ついには、我が国全体の‟旧体制”を焼き尽くし、浄化して行きました。

今日に生きる我々は、いかなる‟志”を持って生くべきか❣
『志を立てて もって 万事の源となす』



コメント